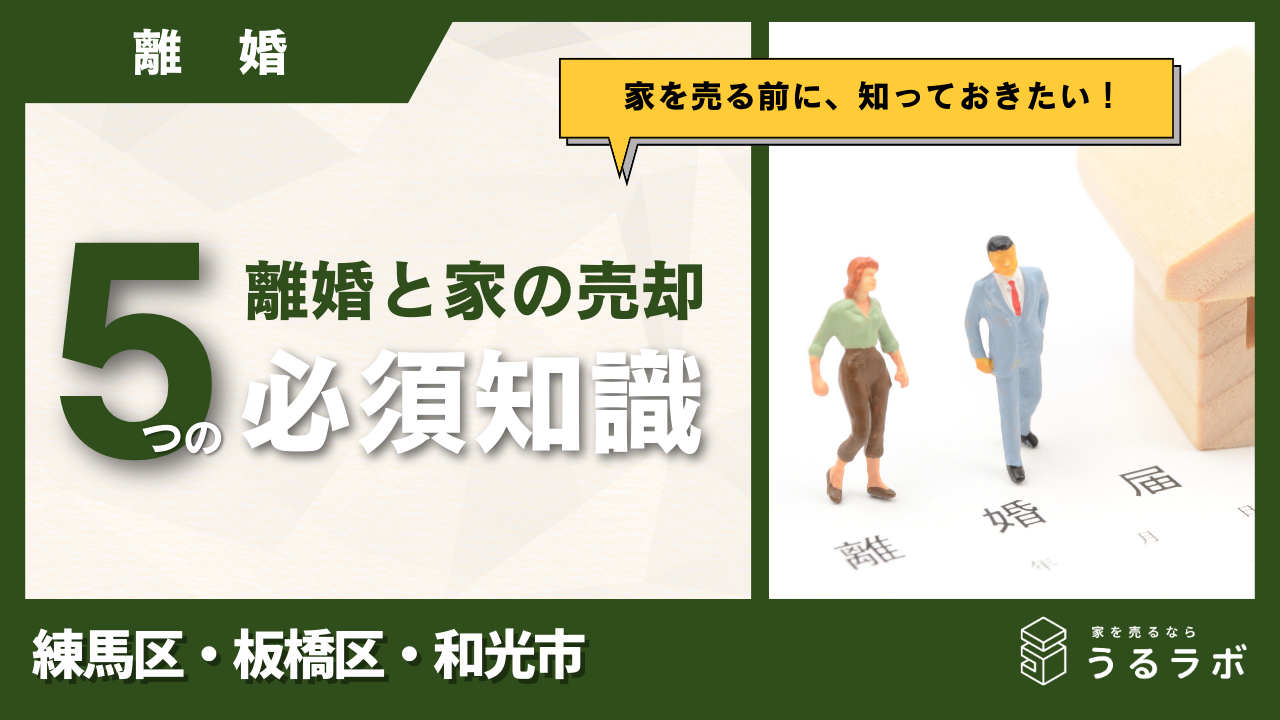
目次
離婚は人生の大きな転機です。お二人がこれまで築き上げてきた生活の基盤である不動産をどうするかは、離婚協議の中でも特に重要かつ複雑な問題の一つでしょう。特に、夫婦で共有名義にしている不動産の場合、「売却したいけれど何から手をつければいいかわからない」「名義や共有持分がどうなっているかよくわからない」「住宅ローンが残っているが売れるのか?」といった不安や疑問を抱えている方は少なくありません。うるラボへのご相談も相続関連に次いで増加しています。
この記事では、離婚を機に共有名義の不動産を売却する際に知っておくべき重要なポイントを、初心者の方にもわかりやすく解説します。不動産をスムーズに、そして後悔なく売却し、新生活をスタートするためのヒントとして、ぜひお役立てください。
離婚に際して共有名義の不動産を売却する場合、離婚前に売却を済ませるのか、それとも離婚後に売却するのか、というタイミングの問題がまず生じます。
多くの専門家は、可能な限り離婚前に売却手続きを完了させることを推奨しています。その理由は、離婚後に共同で手続きを行うことが精神的、物理的に困難になるケースが多いためです。離婚後、元配偶者との連絡が途絶えたり、協力が得られなくなったりすると、売却手続きがストップしてしまうリスクがあります。不動産の売却には、書類の準備や署名、印鑑証明書の取得など、共同で行うべき手続きが数多くあります。これらの手続きを円滑に進めるためには、まだ信頼関係が完全に失われていない離婚前の方がスムーズに進めやすいと言えます。
しかし、状況によっては離婚前に売却が間に合わないこともあるでしょう。その場合は、離婚協議書や公正証書に「不動産の売却に関する取り決め」を詳細に記載しておくことが非常に重要です。例えば、「売却活動は〇〇が行い、売却価格は〇〇円を下回らないものとする」「売却にかかる費用は〇〇が負担し、売却益は〇〇の割合で分配する」といった具体的な内容を明記しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
共有名義の不動産は、**共有者全員の同意がないと売却できません。**これは民法で定められている基本的なルールです。たとえ共有持分が99%あったとしても、残りの1%の共有者の同意がなければ、その不動産全体を売却することは不可能です。
「自分は売却したいけれど、相手が同意してくれない」というケースは珍しくありません。相手が売却に反対する理由には、「住み続けたい」「売却価格に納得がいかない」「単に売却手続きに協力したくない」など、さまざまなものがあります。
このような場合、話し合いを重ねて合意形成を目指すことが第一歩です。第三者である弁護士や不動産会社を交えて交渉するのも一つの手です。それでも合意が得られない場合は、共有物分割請求訴訟という法的な手段に訴えることもできます。この訴訟では、裁判所が不動産の売却を命じる判決を下すことがありますが、時間や費用がかかるうえ、最終的に必ず売却できるとは限りません。まずは話し合いによる解決を模索することが重要です。
共有名義の不動産を売却して得た利益は、財産分与の対象となります。売却益をどう分配するかは、離婚協議において特に揉めやすいポイントです。
分配方法として最も一般的なのは、共有持分割合に応じて分配するケースです。例えば、夫50%、妻50%の持分であれば、売却益も半分ずつに分配されます。
しかし、持分割合だけでは公平性に欠ける場合があります。例えば、夫の単独名義で購入した物件を、後に妻が一部負担して共有名義にした場合や、ローンの返済をどちらか一方が多く負担していた場合などです。このようなケースでは、名義上の持分割合とは別に、これまでの貢献度を考慮して分配割合を決めることも可能です。
重要なのは、お互いが納得できる分配方法を事前に協議し、離婚協議書や公正証書に具体的に明記しておくことです。口約束だけでは後々のトラブルの火種となります。「売却価格から諸費用(仲介手数料、印紙代、測量費、税金など)を差し引いた金額を、〇〇が〇〇%、〇〇が〇〇%の割合で分配する」といったように、詳細な金額や割合を具体的に記載しましょう。
共有名義の不動産に住宅ローンが残っている場合、話はさらに複雑になります。住宅ローンが残っている物件を売却する場合、原則として売却価格でローンを一括返済する必要があります。売却価格がローンの残債を上回る、いわゆるアンダーローンの状態であれば、ローンを完済して売却することができます。
しかし、売却価格がローンの残債を下回る、いわゆるオーバーローンの状態であれば、売却してもローンを完済できません。この場合、不足分を現金で補う必要がありますが、その資金をどう捻出するか、誰が負担するのかを事前に決めておく必要があります。
また、連帯債務者や連帯保証人になっている場合は特に注意が必要です。離婚によってローンの名義や保証人を変更することは、銀行の審査が必要であり、非常に困難なケースが多いです。名義変更ができない場合、たとえ離婚して別々の生活を送っていても、ローンの契約上は引き続き返済義務が残ります。元配偶者がローン返済を滞納すると、連帯債務者や連帯保証人に返済義務が生じ、ご自身の信用情報にも影響が出る可能性があります。
必ず金融機関に相談し、ローンの残債や契約状況を確認した上で、売却後の返済計画を立てましょう。
不動産を売却して利益が出た場合、その利益に対して譲渡所得税が課税されます。譲渡所得税は、不動産の所有期間によって税率が変わるのが特徴です。
長期譲渡所得の方が税率が低いため、所有期間が5年を超えているかどうかは非常に重要なポイントです。
また、マイホーム(居住用財産)を売却した際に適用できる特例もあります。例えば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」を利用すれば、売却益から最高3,000万円までを控除することが可能です。この特例を適用できるかどうかは、不動産を実際に居住用として使用していたかなど、細かな要件がありますので、事前に確認が必要です。
離婚時に共有名義の不動産を売却する場合、特例を適用できるのは名義人であるお二人それぞれです。ご自身の分については、ご自身で確定申告を行う必要があります。税金に関する問題は複雑なため、税理士や不動産会社などの専門家にも相談することをおすすめします。
離婚時の共有名義不動産の売却は、財産分与やローン、税金など、さまざまな問題が絡み合う複雑な手続きです。しかし、事前にポイントを押さえておくことで、後悔のないスムーズな売却を目指すことができます。
この記事で挙げた5つの注意点を参考に、ご夫婦でよく話し合い、必要に応じて専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていくことが大切です。
「何から手を付ければいいんだろう?」こう思われたら、迷わずお気軽に「うるラボ」にご相談ください。


売るか決めていなくても大丈夫。
まずは30秒で悩みを
整理してみませんか?

皆さまから “話しやすい” と
言っていただける
空気づくりを心がけています。